ChatGPTや画像生成AIなど、AIがどんどん身近になってきましたね。
SNSを見ていても「AIで仕事がなくなる」「AIで何でも作れる!」など、いろんな声があります。
でも実際にAIを“学ぶ”立場になってみて気づいたのは、AIを使いこなすには「知識」よりも「考え方」が大事だということ。
私は昨年、「AI実装検定B級」を2週間の独学で受験し、無事に合格しました。
-
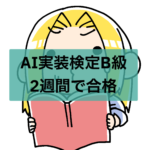
-
AI実装検定B級を2週間で合格した記録
AI実装試験B級を旦那さまにバレずに取得した記録です。
続きを見る
勉強の後に感じたことなど、“学ぶ側”の視点から少しお話ししたいと思います。
AIを知ることは、人を知ることだった
AIについて勉強してまず驚いたのは、「AIって人間の模倣なんだ」ということ。
AIは大量のデータからパターンを見つけ、そこから“次に起こること”を予測します。
でもそれって、私たち人間が「経験」から学んでいくのとまったく同じ仕組みなんですよね。
たとえば誰かの表情を見て「今ちょっと機嫌が悪そう」と感じるのも、過去の経験の積み重ね。
AIもまた、似たような状況を何度も学びながら“推測”しているだけ。
AIを理解しようとすればするほど、「人間ってどう考えてるんだろう?」という原点に戻っていく感覚がありました。
だからこそ、AIリテラシーって単に「AIの知識」じゃなくて、
『自分の思考を客観的に見る力』なのかもしれません。
正確さよりも「問いの立て方」が大事
ChatGPTを使っていると感じるのが、AIの答えは質問次第でまったく変わるということ。
同じテーマでも、聞き方を少し変えるだけで、全然違う視点の答えが返ってきます。
AI検定の勉強中も、「正しい答えを覚える」より「どうやって考えるか」を問われる場面が多くありました。
AIの世界では、「正解を出す」ことよりも「良い問いを立てる」ことが価値になる。
これって、私たちの仕事や日常にもすごく通じると思うんです。
たとえば美容の世界でも、「何を使えばいいか」ではなく「なぜそれを使いたいか」が大事。
AIリテラシーも同じで、自分の中の“目的”や“疑問”を整理する力が必要なんだと感じました。
実例を上げると「お肌が乾燥する時は、何を使えば良い?」だとAIは理論上もっとも正しい保湿のアイテムを進めてきます。
がむしゃらに試したいのであれば、それでも良いですが自分の肌の状況と保湿の種類とで合う合わないが出てくるので、自分が求めてるとものと違う回答帰ってきてしまします。
前提として、苦手な成分を指定したり、水分を抱え込む力欲しいのか、蓄える力が欲しいのか、または乾燥させない力が欲しいのか、何が必要なのか自分の肌状況を伝えた上で、どうしたら良いのか聞くほうが圧倒的に回答のパフォーマンスが上がります↗↗↗
なので、自分の知識以上の質問は出来ないので「AIで何でも出来る」は正確には不正解です。
ゆるコンピュータ科学ラジオの堀本さんも「AIは自分の能力以上のことは出来ない」って言ってました。
本当に知識が無いことは質問できないですもんね。
例えば私が盆栽について何も知らない状態で、質問しようとしても、「盆栽ってどんな種類がある?」とか「盆栽の育て方は?」と聞くだけAIを使いこなしてる聞き方にはなりません。
たとえ目の前に盆栽があっても名前もわからないし、せいぜい写真を送って、盆栽の種類を教えてもらうところから始まるでしょう。
しかも「これだよ」と回答が来たら、そうなのかと思うだけで合ってるのか間違ってるのかも良くわからないww
やはり自分の知識が必要になってきます。
なのでAIリテラシーも自分の目的や疑問を整理する力が軸になると感じました。
AIを怖がらないための、ちょうどいい距離感
SNSでは「AIに仕事を奪われる」という言葉をよく見ます。
でも、AIを実際に勉強してみて思ったのは、AIは敵ではなくパートナーだということ。
AIは人間の代わりではなく、人間を支えるツール。
たとえば私は、文章の構成をAIに相談したり、データ分析を補助してもらうこともあります。
AIに任せられるところは任せて、人間にしかできない「感性」や「判断」に集中すればいい。
リテラシーとは、AIを盲信しないことでも、拒絶することでもなく、
適切な距離感でつきあう力のことだと思います。
リテラシーとは別で私のAIとの距離感はべったりです💦
最近は仕事でも1日中べったりで、濃密に支えてもらっています。
そのおかげで作業効率は飛躍的に上がっています✨️
プライベートでも自分の不調から夕飯の提案まで生活に密着して支えてもらってます。
AIを恐れている事は無いですが、依存しすぎている気もします。
それが良くないことなのかは今後わかることです。
スマホだって出てきた当初は怖がられていたのに、いつのまにか日常に溶け込んで依存症の人が増えています。
スマホ依存が悪とする一方でスマホがないと仕事にならないとか生活で出来ないと日常に支障をきたす人もいます。
AIもそのうち依存症の人が出てAI依存が悪とされる日が来るかもしれません。
でも私はべったりな距離感で今のAIと私で出来る機能を満喫しています。
AI依存が悪とされたら、その時に考えましょうかね。
「学び続ける姿勢」こそがAIリテラシー
AIの世界は、日々アップデートされています。
昨日の常識が、明日にはもう古くなっている。
だからこそ、AIを完全に理解するよりも、学び続ける姿勢が大切です。
私にとってAI実装検定B級試験の2週間は、知識を詰め込む時間ではなく、「分からないことを楽しめるようになる」時間でした。
AIリテラシーとは、情報を覚える力ではなく、変化を恐れず、学び続ける好奇心を持つこと。
それが、この時代を“自分らしく”生きるための最大のスキルだと思います。
最後に私が日常的に依存してるAIについて記録している記事があるのでご紹介。
↓↓↓
-

-
【AI】動画生成AIを楽しむ会(Sora2が使えた喜び)
AI実装検定B級の私が、AIで動画や画像を作成して楽しんだ記録です。 使用したAI一覧 保守派ですが比較的AIには前向きなちゃんみー。です。 何と言ってもAI実装検定B級を保持していますからw そんな ...
続きを見る
良かったら見てみてくださいね☆